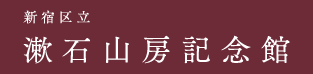4月上旬の良く晴れた日、西武バスに乗りました。
休みの日には、市町村立の地域博物館を見学して回るのが趣味になっています。

平林寺山門
通過することを知りました。博物館めぐりのついでに歴史ある神社仏閣を巡ることも小旅行の醍醐味です。
平林寺は永和元(1375)年、京都天龍寺や鎌倉の円覚寺・建長寺の住持にもなった
石室善玖(せきしつ・ぜんきゅう)によって岩槻に創建され、寛文3(1663)年川越藩主の松平輝綱によって
現在地に移転した禅寺です。私事になりますが、学生時代の恩師が平林寺史を編纂しており
一度は参拝したいと思っていましたので、正に渡りに船でした。
バス停「平林寺」から少し歩くと、バス通りに面して総門があります。
入山受付で拝観料をお渡しし、御朱印も頂いて、広い境内に足を踏み入れました。
平林寺は現在でも臨済宗妙心寺派の修行道場ですので、本堂や僧堂の周囲には立ち入ることは出来ません。
しかし、境内の大半を占める国指定天然記念物の境内林は、東京ドーム9個分もの雑木林で、
往時の武蔵野を思わせる大変自然豊かで落ち着いた空間でした。
入口の大きな「境内案内図」には、武田信玄次女の墓と増田長盛の墓が図示してあります。
信玄次女は見性院。穴山梅雪の妻で、のちに保科正之を養育したことでも知られます。
増田長盛は豊臣家の五奉行の一人です。その先には、「智慧伊豆」こと江戸幕府老中の松平信綱と
その正室を中心とした大河内松平家の墓域や玉川上水の開削に尽力した安松金右衛門の墓もあります。
見性院と増田長盛の墓にお参りし、大河内松平家の墓地に向かおうと思って、
改めて墓地の案内板に目をやると、見性院と増田長盛の墓の並びに「前田卓の墓」という記載がありました。

前田卓・利鎌墓
ここ平林寺にあったのです。このこと自体は知っていましたが、ここに来るまで全く思い出さず、
危うくお参りしそこねるところでした。墓には詳しい「解説板」もありました
(入山受付で配布されているパンフレットには「十墓巡礼」としてきちんと紹介されています)。
前田卓(つな)(1868-1938)は、熊本県玉名郡小天の自由民権家・前田案山子(かがし)の
次女として生まれました。案山子は熊本における自由民権運動の中心的人物であり、
明治23(1890)年の第1回衆議院選挙で国会議員になっています。卓はそのような環境で成長し、
熊本の自由民権家と結婚しますが離婚し、小天村に戻り、案山子の温泉付き別邸だった旅館で暮らしていました。
熊本五高の教師だった漱石が訪れたのはそうした時のことです。案山子の死去後、明治38(1905)年、卓は上京し、
この年に結成されたばかりの中国同盟会の機関誌を発行する民報社に住み込みで働き、
ここに集う革命家や中国人留学生の世話をし、中国革命を支援したことで知られます。
墓石は正面左に卓の戒名「雪庭院然松慧卓大姉」。その右に「甚快院南泉利鎌居士」という
男性の戒名があります。これは30歳下の異母弟で、のちに自らの養子にした前田利鎌(とがま)(1898-1931)
のことです。小天温泉を訪れた漱石に頭を撫でられたこともあったといいます。
利鎌は東京の小学校に転校後、千駄木の郁文館中学に進みます。
この頃、早稲田穴八幡宮で漱石と再会しています。卓も一緒だったかもしれません。
大正4(1915)年、第一高等学校に進学。卓の養子となりました。
そして、大正5(1916)年4月頃から漱石山房に出入りするようになります。
漱石逝去の8ヵ月前のことでした。すなわち利鎌は漱石最晩年の弟子であり、
おそらく最も若い門下生だったと言えます。大正8(1919)年、東京帝国大学文学部哲学科に進学。
のち東京工業大学教授となり、学生と共に熱心に平林寺に参禅しましたが、32歳の若さで病死。
代表作に『臨済・荘子』『宗教的人間』があります。東大哲学科の先輩でもある
漱石長女の夫・松岡譲と交際したことでも知られます。
二人の墓は刻銘により、利鎌逝去の年の昭和6(1931)年4月11日に卓が建立したものであることがわかります。
墓石左側面には利鎌の忌日(1月17日)が刻まれていますが、卓の命日は刻まれていません。
通常は夫婦の墓石となるのでしょうが、二人とも独身のまま亡くなったため、このような形になったのでしょう。
晩年の卓は東京市養育院板橋分院に勤め、孤児に慕われつつ、昭和13(1938)年、
71歳で亡くなりました。二人の評伝は、安住恭子著『『草枕』の那美と辛亥革命』(白水社、2012年)、
同著『禅と浪漫の哲学者・前田利鎌』(白水社、2021年)に詳しく紹介されています。
(学芸員 今野慶信)
テーマ:漱石について 2025年4月26日